 内田さんは、あるタレントの演技に対する自分の意見をSNSに投稿しました。しかし内容が悪口と捉えられたのか・・・誤解され、誹謗中傷の対象となっています。内田さんは、誤解を解くためにどう対応するのがいいのでしょうか?正しいと思うのを選択してください。
内田さんは、あるタレントの演技に対する自分の意見をSNSに投稿しました。しかし内容が悪口と捉えられたのか・・・誤解され、誹謗中傷の対象となっています。内田さんは、誤解を解くためにどう対応するのがいいのでしょうか?正しいと思うのを選択してください。
| ア | 投稿そのものを削除する。 |
| イ | 誤解を招いたと思う表現を修正し、再投稿する。 |
| ウ | 法的手段で訴えることを考える。 | エ | 放置する。 |
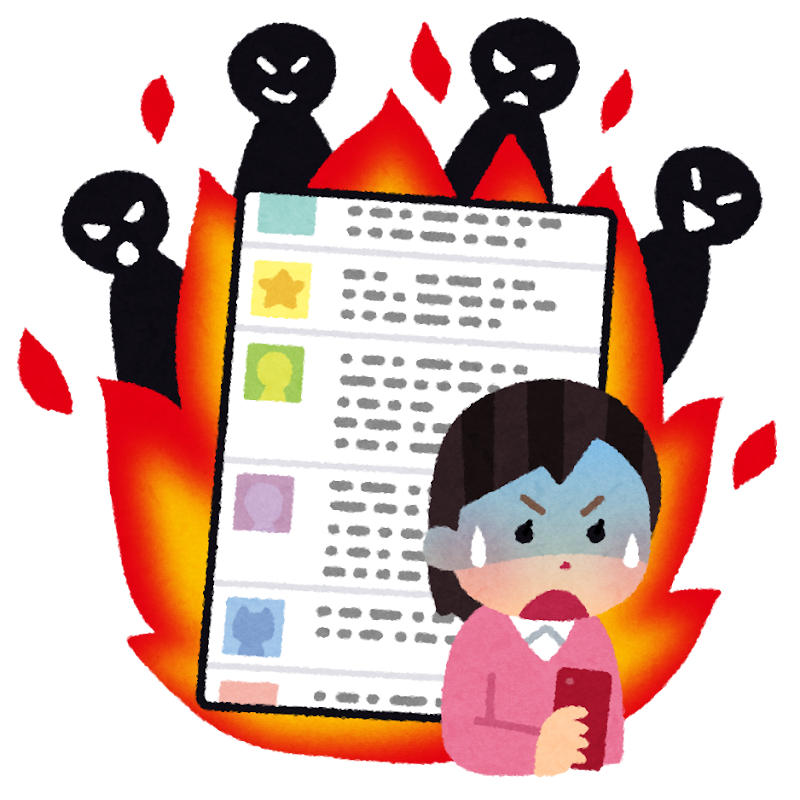
答え:イ
誹謗中傷に対する対応は、非常に難しく、どのような対応をしてもストレスを受けます。相手の人格を否定するような投稿は避けるべきでしょう。そのうえで、もし誤解を招くような表現をしていたのであれば、それを解くために冷静な対応するのが望ましいといえます。
誹謗中傷を受けた際、ストレスを軽減するため、投稿そのものを消したり、放置するのもひとつの方法です。ただ、それによるリスクもあります。
SNSは拡散が可能です。投稿内容が拡散されてしまった場合は、削除しても問題が解決しないかもしれません。投稿が「削除された」という事実で、さらに悪い状況が拡散する可能性もあります。
放置すると、誹謗中傷に憶測がつくかもしれません。誹謗中傷より広がり、それを見たくない人にとっては、不快でしょう。削除や放置をするより、ミュートやブロックなどで、相手を「見えなくする」方が対処策としては、賢明だと思います。
法的手段に訴えるのも選択としてはありです。ただ、最終手段と捉えるのがいいでしょう。
誹謗中傷が収まらない場合は、SNSの機能を使って、誹謗中傷や嫌がらせを「報告」するのもいいでしょう。「報告」することで、SNSのプラットフォーム側が問題のある投稿やアカウントに対して適切な対応を取ることができます。
SNSプラットフォームでは、誹謗中傷や嫌がらせに関する報告の審査に、AI技術と人間による審査を組み合わせて対応してます。投稿に対するフィルタリングはAIが行います。AIが投稿内容を解析し、コミュニティのガイドラインに違反しているかどうかを判断します。その結果、明確な規定違反であると判断される場合、AIは自動的に投稿を削除したり、アカウントに対して一時的な制限をかけたりすることがあります。
AI技術はすごい勢いで進化しています。AIは単なる一文だけで判断するのではなく「文脈」を理解する学習をしてます。AIモデルを構築するエンジニアにとって「文脈の理解」は主要なテーマでもあります。投稿に対する判断は、批判的な意見と、誹謗中傷を区別する必要があります。特定の発言だけで判断するのではなく、発言者がこれまでどのような言動を繰り返してきたかを分析する必要があります。
もちろん、AIだけで完結しない疑わしいケースもあるので、そこは人間による審査が絡んできます。
誹謗中傷で受けるストレスを専門の窓口に相談することも考えるのもいいでしょう。
www.mhlw.go.jp
誹謗中傷を受けたら、冷静な対処をするよう心がけましょう。